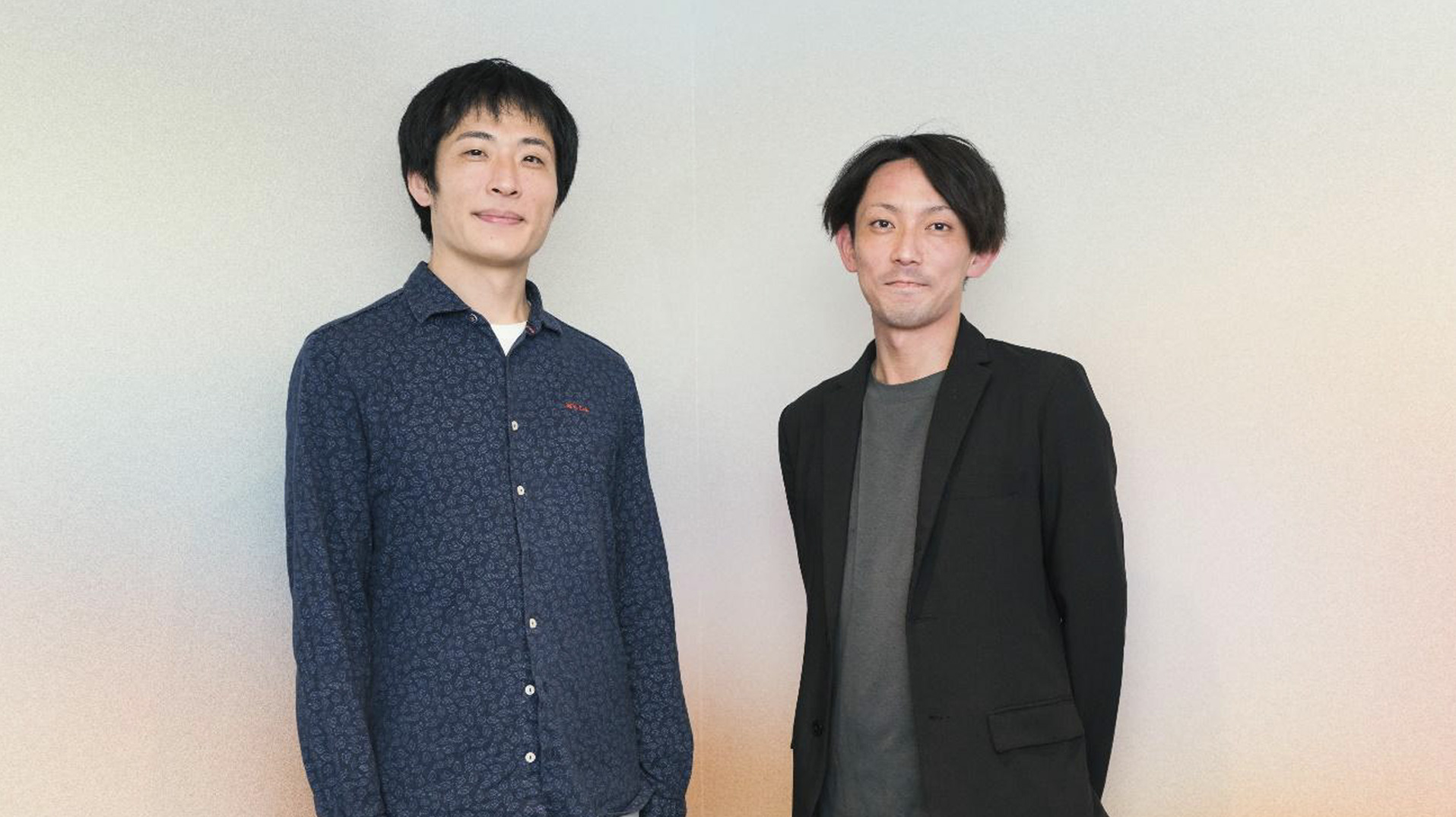
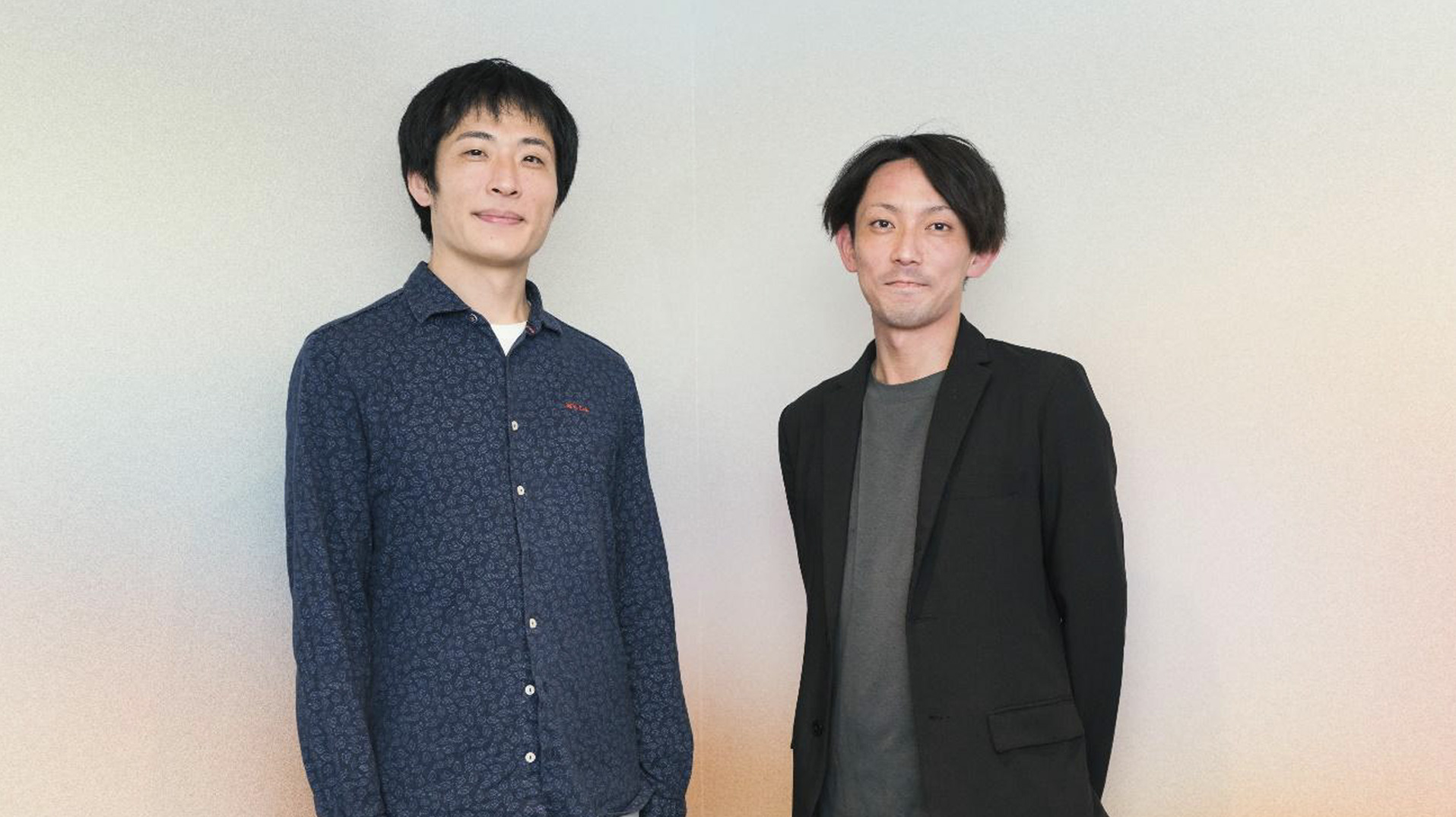
東京コンソーシアム会員のインテグリカルチャー株式会社は、細胞農業の発展を目指すベンチャー企業です。細胞農業とは、動物から採取した細胞を培養して増やし、培養肉や皮革などの製品を作り出す技術で持続可能な食糧生産の新しい方法として注目されています。本対談では、東京コンソーシアム・ディープ・エコシステム支援でインテグリカルチャー株式会社を担当し、伴走者として支援をしてきた小澤真彦氏が、羽生雄毅代表取締役に、これまでの活動事例や今後の事業展望について話を聞きました。
羽生 雄毅[写真左](インテグリカルチャー株式会社)
聞き手・進行:小澤 真彦[写真右](東京コンソーシアム ディープ・エコシステム)
(敬称略)
小澤:まずは、羽生さんがインテグリカルチャーを立ち上げた経緯について、お聞かせください。
羽生:もともと、私はSFの世界に憧れやロマンを感じて理系の道に進みました。大学の博士課程ではナノテクノロジーを研究していて、卒業後は環境エネルギー分野に携わっていました。しかし、もっとSFの世界を体現したいという気持ちが強くなり、いろいろなアイデアが浮かぶ中で、現実的に挑戦できる分野として「培養肉」にたどり着きました。
実際、その分野に取り組もうとしたものの、資金も知識もなく、メンバー集めも難しい。それに、こうした社会を変えるような革新が既存の体制から生まれても面白くないと感じ、オープンソースプロジェクトとして世に広めようと考えました。最初は“半ビジネス”のような形でオープンソースプロジェクトを始めました。その過程でいろいろと人が集まってきてできたものが「Shojinmeat Project」という、いわゆる同人サークルです。今でも活動は続いていて、同人誌を出したり、技術書を発表したりしています。
こうして多くの人が集まり、細胞農業について議論を進めていく中で、「この技術が社会に出る際に、1つの大企業が独占する状態にはロマンを感じない」「遺伝子組み換え食品のように反発を招く恐れがある」と考えました。そこで、必要になるのはエコシステムです。技術を社会に普及させるための営利団体や、政府やアカデミーを巻き込んでルール作りをする非営利団体、そして、本当に最先端なことを大人の事情に縛られずにできるのはアーティストやシチズンサイエンスだったりしますから、同人サークルも必要だろうと。このような役割を持つ、「日本細胞農業協会」、「インテグリカルチャー株式会社」、「Shojinmeat」といった団体が連携し、社会実装の核を作るべきだと考えました。
このエコシステムの考え方は、弊社のビジョンにも通じています。インテグリカルチャーが目指すのは「みんなが使える細胞農業」です。細胞農業インフラを整え、様々な人がこのインフラを使って新しいものを生み出せる社会を実現したいと考えています。
小澤:ありがとうございます。いろいろな研究テーマがある中で、なぜ培養肉にフォーカスされたのですか?
羽生:本当にいろいろなテーマがありますよね。火星コロニーやマスドライバー(※)など、やりたいことはたくさんあります。ただ、現実的に「今取り組むなら何か」と考えたとき、培養肉に可能性を感じたのです。21世紀の半ばには培養肉がメジャーになるだろうと考えましたし、物理的に不可能ではないことも大きな理由です。
※SF作品に登場する、貨物や宇宙船を宇宙へ輸送する技術
小澤:SFの中で、培養肉が登場する作品で印象に残っているものはありますか?
羽生:あまりに多すぎて、特定の作品は覚えていないのですが、SFの世界観として普通に出てくることが多いですね。私は「SFの世界観」が好きで、作品そのものや文学が好きというわけではないのです。これは、従来のSFファンとは少し違った視点かもしれませんね。
小澤:なるほど。話を戻しますと、インテグリカルチャーや日本細胞農業協会、Shojinmeatはそれぞれ具体的にはどのような役割を担っているのか教えてください。
羽生:例えば、日本細胞農業協会では8月29日に「細胞農業会議」という学会を開催し、多くの研究者が集まって研究発表を行いました。文科省や他の省庁、企業の方も参加し、大盛況でした。学会では、アカデミックな議論が中心で、技術的にどこまで進んでいるのかといったことや、方法論について、非常にピュアな議論が行われたということが良かったと思います。
一方で、「Shojinmeat」は、メンバーシップや定義もなく、みんなで自由に集まって活動する同人サークルです。自宅で培養肉を作ったり、アート作品を作ったり、クリエイターを支援したりと、自由に活動しています。ニコニコ動画で「培養肉作って食べてみた」という動画を投稿したこともあります。
小澤:ニコニコ動画ですか、それは面白いですね。
羽生:最近は「バイオアーティスト」たちが細胞培養を用いて作品を作る活動が目立っています。一般的なアート表現といえば、描いたり彫ったり、捏ねたりといった手法が主流ですが、バイオアートでは「育てる」という方法で作品を創造します。そういう意味では、盆栽はバイオアートの先駆けとも言えるでしょう。私たちは、この「育てる」ことで形を作り上げる作品制作をいくつか支援してきました。最近では、国立新美術館で「LOM BABY」という名前で、「龍の肉」という作品を展示している方もいました。
小澤:本当に面白いですね。日本でこういった活動をしている方は非常に限られていると思いますし、非常にユニークで尖っていると感じます。それが、インテグリカルチャーの姿にも反映されているのではないかと思いますし、その思いがあるからこそ現在のインテグリカルチャーが生まれたのだとも感じます。

小澤:インテグリカルチャーの役割についても教えていただけますか。
羽生:インテグリカルチャーは、信頼される社会インフラを作ることを目的としています。つまり、我々のビジョンである「みんなが使える細胞農業」を実現し、安心して利用できるインフラを提供することを目指しています。
小澤:そこにはどのような思いが込められているのでしょうか?
羽生:Shojinmeatや細胞農業、そしてインテグリカルチャーに共通するのは、「文化を増やす」というスピリットです。文化を増やすための手段として、「みんなが使える細胞農業」を目指しています。そこで作るものは「ナマモノ」です。製品は食品かもしれないし、化粧品かもしれない、はたまた細胞部品かもしれない。先ほどのバイオアートや、東京大学の竹内 昌治教授(※)が研究している「筋肉で動くロボット」も含まれると思います。そうした「ナマモノ」を作ることによって、新たな文化が生まれてほしいと願っています。
※竹内 昌治(たけうち まさはる)教授・・・東京大学工学系研究科教授である。生物学と工学を融合させ、新技術を開発するバイオエンジニアリングや、マイクロスケールの流体制御技術を用いて、バイオセンサーやラボオンチップ(Lab-on-a-Chip)デバイスの開発を行うマイクロ流体デバイス、また、細胞の操作や解析を行うための新しい技術を開発する細胞工学を専門領域とする研究者である。
小澤:そのナマモノ作りが、現在のインテグリカルチャーの事業にも反映されているのですね。具体的に、食品や化粧品など、どのような事業が進んでいるのか教えていただけますか?
羽生:ナマモノ作りの事業としては、今できるものと将来実現できるもの、また安価にできるものとコストがかかるものがあると思います。その中で、現時点で採算が取れて実現可能なものとして最初に手がけたのが、化粧品分野です。
小澤:化粧品が最初なのですね。
羽生:はい、「セルアグコスメ」がナマモノの一種です。例えばヒト幹細胞培養やコラーゲンなど、生き物由来の成分を扱う分野です。動物由来の成分を使うために動物を殺すのは望ましくないという意見もあり、一般的には食料生産の副産物を活用していますが、供給の安定性に課題がある。その点、細胞培養で化粧品の原材料を作ることで、供給の安定性を確保できます。
小澤:確かに植物性の成分は多く見られますが、動物性のほうが効果を実感できる面もありますよね。
羽生:そうです。鶏卵由来の素材は効果を感じられる成分の一例ですが、鳥インフルエンザの流行で供給が止まるなど、不安定さが課題です。
小澤:アンチエイジングコスメの市場規模はどのくらいあるのでしょうか?
羽生:国内では約4000億円と認識しています。私たちのようなベンチャーには大きな市場です。初期段階では採算が取れる化粧品分野に注力しましたが、次に、採算が取れそうな分野として、入手困難な食品、例えばフォアグラのような高級食材を視野に入れています。ちなみに一般的なステーキ肉は複雑な肉構造を持つため、培養肉で作るのは、再生医療で培養心臓を作るくらい技術的なハードルが高く、実現するにはまだまだ時間を要します。
小澤:フォアグラは実際に開発中ですよね。味や食感の再現性はどうですか?
羽生:再現する技術の開発は進んでいますが、あとはそれを安定的に生産できるのか、という話になってきますね。そもそも、本物に似せるかどうかは別の議論があります。ここで興味深かったのが、培養したてのフォアグラの原材料に対して、シェフの方が非常に興味を持ってくれた点です。「誰も扱ったことのない食材だから挑戦したい」、「俺が調理するから加工せずそのまま渡してほしい」というように、盛り上がってくれているシェフの方が複数名いらっしゃいます。我々がフォアグラに似せようとするのではなくて、プロのシェフに任せたほうが、新しい文化が増えるという点からもいいのではないかとすら思っています。考えてみれば当然かもしれません。シェフは常に新しい味を求める職人ですから、このグシャっとした細胞の塊ですら、新たな素材として挑戦したくなるのでしょう。

小澤:それはスタートアップのマーケット開拓と似ていますね。新しいものを創造する点でシェフもスタートアップも共通しています。
羽生:そうですね。世の中には、細胞培養肉を「代替食」と捉える向きもありますが、私はそうではなく、まったく新しい食文化だと考えています。代替食ではなく「新感食」ですね。
小澤:そういう意味では、代替肉と見なされてしまい、「まったく新しいもの」として受け入れてもらえないという課題があるのでしょうか?
羽生:今後、そういった認識が広がる可能性もあるため、メッセージの伝え方が重要になると思います。これに関しては、ブランディング戦略が鍵を握るポイントですね。
小澤:インテグリカルチャーとして、現在どのような課題を感じていますか? もちろんブランディングの問題もあると思いますが、会社や社会全体として課題だと考えている点があれば教えてください。
羽生:課題を考える際に、まず確立しなければならないのは「低コストで安定的に大量生産できること」です。この点が確立できていないと、消費者ニーズやブランディングといった議論もすべて机上の空論に過ぎません。ですので、今はこの部分に集中して取り組んでいます。
小澤:安定的に生産するためには、やはりさらに研究を進めて、大量生産のシステムを導入する必要があるのですか?
羽生:そうです。しかし、その生産システム自体がまだ市販されていないため、自ら開発する必要があります。そこで、共同研究開発が重要になってくるわけです。この部分は弊社が最も力を入れて取り組んでいるところです。
小澤:例えば、具体的な研究内容について、言える範囲で教えていただけますか?
羽生:弊社のアプローチとして、まず「川上のプレイヤー」、つまりバイオリアクターや原材料を提供する企業があり、次に「川下のプレイヤー」、すなわち食品会社や化粧品会社、健康食品会社といった消費者向け製品を作る企業があります。両方がそろわないと、細胞農業は成り立ちません。しかし、細胞農業は新しい分野であるため、参入企業も手探りの状態です。
そこで、細胞農業の道筋を明確にすることが弊社の役割です。その道筋が明確になれば、「うちはここが得意です」といった形で川上・川下双方の企業が集まりやすくなります。幸い現在では、その流れが現実となり始めています。
具体的な事例として、「川下」のプレイヤーであるマルハニチロさんと、細胞培養技術による魚介類の生産に取組んでいます。一方、「川上」ではCulNetコンソーシアム(※)が連携しています。例えばラピッドプロトタイピングに強みがある墨田区の浜野製作所さんや、他にも素材メーカーなどが参加しています。
※CulNetコンソーシアムとは、細胞農業の実用化と普及を目的としたオープンイノベーションプラットフォームで、インテグリカルチャーが主導している。主な目的は、細胞培養を促進するための技術・インフラの整備と、効率的な生産システムの構築。参加企業が連携し、細胞培養の大規模生産やコスト削減といった課題解決を目指している。
小澤:CulNetコンソーシアムには、どんどん人が集まっているようですね。

羽生:そうですね。現在は16社ほどが参加しており、成果も着実にあがってきています。
小澤:コンソーシアムを立ち上げたのはいつ頃ですか?
羽生:2021年4月1日に設立しました。今では、コンソーシアムメンバーの企業が開発した製品をシンガポールで行われる細胞農業関連の見本市で展示し、実際に販売する段階にまで来ています。日本では、細胞農業分野に対する投資が少ないと言われることもありますが、実際には細胞農業に貢献し得る技術を持つ企業が多数あります。
小澤:こうした技術を持つ企業には、具体的にどのような会社が多いのですか?
羽生:主に素材メーカーや製造系の企業が多いですね。
小澤:インテグリカルチャーとして、コンソーシアムにもっと参加してほしい業種や技術を持つ企業はありますか?
羽生:そうですね、特に機械やファクトリーオートメーションの分野、バイオリアクターやバイオプロセスの設計に強いエンジニアリング系の会社です。例えば、工場で作業着を着て溶接を行うような現場の技術を持つ方々です。
小澤:インテグリカルチャーの事業内容からは、そうした企業との関連がわかりにくい部分もありますが、どのように関連しているのでしょうか?
羽生:例えば、連続生産の設備設計や実装を行う企業です。イメージとしては、ヨーグルトや飲料などを製造する大手乳業会社が持つ大型タンクや配管設備を作っているような会社です。
小澤:なるほど、そのような会社が関係してくるわけですね。これまでは、食料や製品を作る企業と関わると思っていましたが、設備そのものを作る企業との連携も必要になります。
羽生:はい、最終的に製品を作る食品企業がバイオリアクターを使って商品化することも重要ですが、まずは細胞性食品を生産できるインフラが不可欠です。この「生産インフラ」と「市場の成立」は車の両輪のように密接に関わっていると思います。現在、技術的なボトルネックは「作れること」を担う川上の部分にありますね。
小澤:川上の生産基盤を整えるには、多額の資金が必要になりそうですね。
羽生:その通りですが、うまくやらないといけない部分でもあります。海外では多額の資金調達を行い、現状の技術で大型設備を導入している例も多いのですが、バブルが弾けて行き詰まっている状態です。海外は細胞農業への投資が盛んだから日本より進んでいると言われがちですが、そうとも言い切れない理由がまさにそこにあります。だからこそCulNetコンソーシアムには意義があります。
小澤:現段階では大規模に展開することが正解ではないということですね。
羽生:いま重要なのは「ラピッドプロトタイピング」、つまり高速の試行錯誤ですね。これをやるには大規模である必要はなく、小規模な生産環境でラピッドプロトタイピングを行い、自動化や連続生産、培養液のリサイクルといった要素を試しながら、CulNetコンソーシアムのみんなで開発を進めています。
小澤:その点について、昨年末に採択されたSBIR(※)の資金が活用されているのでしょうか?
※SBIR(Small Business Innovation Research)とは、政府が中小企業の技術革新を支援するために行う助成制度。研究開発費や新技術の市場展開に必要な資金を提供し、イノベーション促進、ユニコーン創出を目指している
羽生:まさにその通りです。全体的には、スケールアップと安定生産系の構築を進めています。SBIRは4年間のプログラムなので、その間に完了させる予定です。
小澤:川上にあるのがCulNetコンソーシアムだとしたら、川下にあるのが今年の6月に始めた「勝手場(Ocatté Base)」(※)でしょうか。
※勝手場とは、細胞農業で必要な資材を販売するメーカーと細胞農業に関心のある企業を繋げるメンバーシップ型のB to Bマーケットプレイス。「すべてのひとが自由気まま(勝手)に細胞農業に参加できる世界(場)」をミッションにしている
羽生:そうですね。CulNetコンソーシアムで共同開発したものを勝手場に出品し、勝手場のユーザーが実際に使ってフィードバックをCulNetコンソーシアムに返すという形で、川上と川下で意見交換が行われています。

小澤:東京コンソーシアムで支援させていただいてから約1年半が経ちました。その中で、どのような点が良かったですか?
羽生: SBIRへの採択が決まる直前の混乱した時期に、精神的な支えになっていただいたのは心強かったですね。
小澤:SBIR前は、2週間に1回ほど定例でミーティングをさせていただいていましたが、毎回様々な議題があって、資金や顧客獲得、さらに上場までのプロセスについても検討していたと認識しています。
羽生:あの頃は本当に混乱の連続でしたね。SBIRのようなスタートアップの支援制度は今後も続いてほしいですが、重要なのは、コミットメントが希釈化しないところに資金が注がれることで、それが大きな推進力になると感じます。大企業連合の持ち株会社のようなところに資金が入るとコミットメントが希釈化してしまい、期待した成果が得られにくいですが、健全なスタートアップに資金が注がれれば大きく成長すると思います。
小澤:おっしゃる通りですね。ディープテックが今後さらに重要視されていく中で、支援者側としても、どうやって育てていくのか、どうロールモデルを作るかは、我々もまだまだ勉強しないといけません。
羽生:駆け出しの時期のスタートアップは、イスラエルが参考になると思います。尖った技術を持つスタートアップが資金を得られやすい環境がある。ただ、イスラエルは国内市場が小さいので、成長した企業は国外に出ざるを得ないという点が課題です。
小澤:アメリカ市場に進出している企業も多いですよね。

小澤:では、最後に今後の展望についてお伺いします。
羽生:個人的な夢としては「みんなが使える細胞農業」を実現することです。最終的には「ソーラーパンク」の世界にたどり着きたいと思っています。映画『2112年 ドラえもん誕生』のオープニングに出てくるような未来です。
小澤:「ソーラーパンク」については、羽生さんが作成した資料で拝見したことがあります。
羽生:「ソーラーパンク」は、サイバーパンクの対抗軸として考えられています。サイバーパンクが黒や紫、ピンクのイメージなら、ソーラーパンクは白や緑、青のイメージの世界です。例えば、白い未来的なビルが半分以上緑に覆われていたり、タコのような形をした風車が空に浮かんでいたり、太陽光パネルが付いたドローンが物を運んでいたり、企業の看板が一切ないような世界ですね。
小澤:羽生さんが描く未来として、そこに到達するためにはどのような道筋を考えていますか?
羽生:まず、誰もが使える細胞農業のインフラを整えることです。それには、ナマモノを安定的に大量かつ低コストで生産できる技術が必要です。そして、そうした技術が様々な人にアクセス可能な状態であることも重要です。
小澤:それは国内に限らず、世界的な展開を目指しているということですね。
羽生:はい、国内外両方での展開です。ただ、実際にそれを実現できる国は限られており、例えばシンガポールは資金面では強いですが、製造基盤が弱く、ものづくりには向きません。一方、日本やドイツ、中国といった製造基盤の整った国では、現実的にこうしたインフラを整えることが可能です。日本の強みの1つとして、これが勝ち筋になると考えています。
小澤:確かに、日本は「ものづくり大国」として評価されていますからね。
羽生:まだアップデートは必要ですが、産業基盤が整っています。実は、こうした基盤を持つ国はそれほど多くはなく、イギリスやドイツ、中国、アメリカが該当するくらいです。「ものづくり大国」として新しい価値を創造するという、ともすればありふれた表現に聞こえるかもしれませんが、これが大事な点です。
小澤:納得感がありますね。日本の製造基盤を生かし、細胞農業のインフラやシステムを作り上げていくということですね。
羽生:そうですね。
小澤:本日は貴重なお話をありがとうございました。改めて、羽生さんの想いがよくわかりました。
